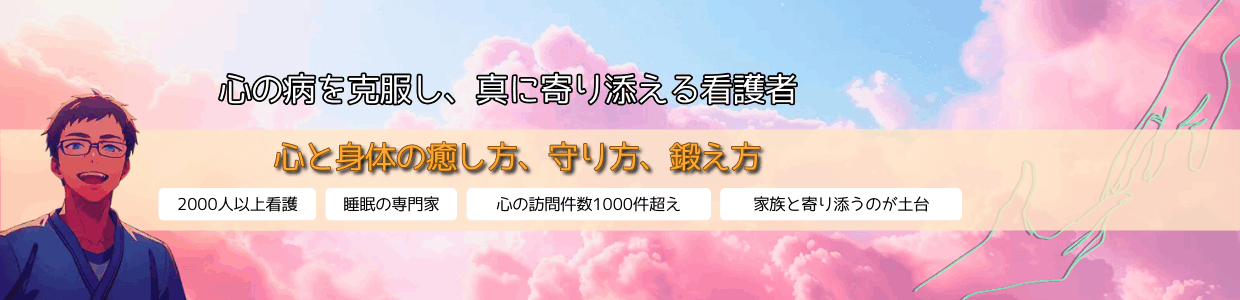プロフィール
はじめまして!
しょうへい@ヒトに寄り添う看護者です。
山梨県出身・在住の看護師として、現在は訪問看護の現場で日々患者さんとそのご家族に寄り添いながら働いています。
妻と2人の子どもたちに支えられながら、父親として、そして看護師として充実した毎日を送っています。
生年月日は1986年8月29日で、偶然にもマイケル・ジャクソンと同じ誕生日です(笑)。
マンガ・アニメ・映画が大好きで、特に『ハンター×ハンター』は何度読み返しても新しい発見があり、冨樫義博先生の深い人間描写に感銘を受けています。
現在は子どもたちと遊ぶ時間が何よりも幸せで、彼らの成長を間近で見守れることに日々感謝しています。
私の看護師としての歩みは決して平坦ではありませんでした。
むしろ、多くの挫折と困難を乗り越えてきた経験こそが、今の私の看護観の根幹を形成しています。
私の経験を率直にお話しさせていただきます。
看護学校時代~現在まで:困難を乗り越えて
挫折からの学び
看護師になって10年以上が経ち、ベテランと呼ばれる域にまで経験を積むことができましたが、看護学校時代は実習が思うようにいかず、深刻な挫折を経験しました。
元々生真面目な性格で、完璧を求めがちだった私は、看護記録がうまく書けないことに強いストレスを感じていました。
睡眠時間を削っても記録が終わらず、精神的に追い詰められる日々。
落ち込むと更に集中力が低下し、より記録が書けなくなるという負のスパイラルに陥りました。
ついには実習に行くことができなくなり、朝起きることさえ困難な状態に。
この時、両親は私の状態を理解し、何も言わずに温かくサポートしてくれました。
「休学」という選択をすることで、一度立ち止まり、自分自身と向き合う時間を得ることができたんです。
再起への道のり
約半年の休養期間中、私は看護師を辞めることは一度も考えませんでした。
むしろ、この挫折が「なぜ看護師になりたいのか」「どんな看護師になりたいのか」を深く考える機会となりました。
復学に向けて、知識を一から見直すことを決意。
基礎看護学から解剖生理学、各論まで、科学的根拠を理解しながら学び直しました。
単に暗記するのではなく、「なぜそうなるのか」「患者さんにとってどんな意味があるのか」を常に考えながら学習を進めました。
この期間の学びが、後に私の看護実践の基盤となりました。
表面的な技術や知識ではなく、患者さんの立場に立って考える視点、科学的根拠に基づいた判断力を身につけることができたのです。
患者さんへの共感の深まり
復学後の実習では、精神的に辛い時期を経験したからこそ、患者さんの苦しみや不安に心から共感できるようになりました。
病気や入院による不安、先の見えない恐怖、家族への心配など、患者さんが抱える様々な感情に対して、以前とは比べものにならないほど深く理解できるようになったんです。
この経験は、看護師になってからも私の核となっています。
技術的なスキルももちろん大切ですが、何よりも「患者さんのために」という看護師として当然の心得を、自然体で持ち続けることができています。
IT業界から看護師への転身
プログラマー時代の挫折
高校卒業後、私はIT系の専門学校に進学し、プログラマーとして社会人生活をスタートしました。
しかし、入社数ヶ月でのトラブル対応により、新人8名で深夜までの残業を余儀なくされ、東京から福岡への長期出張も経験。
1ヶ月で残業時間が100時間を超える過酷な状況でした。
その後の一人での出向では、広いフロアの片隅で孤独な作業を続ける日々。
上司からは「うざがられているが引かずに頑張れ」と言われ、必死に取り組みましたが、「本当に人の役に立っているのだろうか」という疑問が日増しに強くなりました。
次第に休日でも心が晴れない状態が続き、うつ病と診断されました。
それでも仕事は続けましたが、人との関わりが希薄な環境で、「人に関わり、直接人の役に立てる仕事がしたい」という強い思いが芽生えました。
看護師への道を選択
両親の助言と支えにより退職を決意し、1年かけてうつ病から回復。
プログラマーとは違う道を考え、両親が医療従事者だったこともあり、複数の選択肢の中から看護師の道を選びました。
しかし、IT業界での経験は、決して無駄ではありませんでした。
論理的思考、問題解決能力、細かな作業への集中力など、これらのスキルは看護の現場でも大いに活用されています。
特に、患者さんの状態変化を分析し、適切な対応を考える際に、システマティックなアプローチが役立っています。
看護師としての成長を支えた言葉
指導者からの教え
3年目の時の指導者から言われた「退院調整は患者をいかに家族と思えるかだからね」という言葉は、私の看護観を決定づけました。
この言葉により、患者さんを自分の家族のように思い、時には医師とも議論を重ねながら、患者さんやご家族の代弁者として行動する覚悟を持つようになりました。
家族の希望と医療者の判断が対立する場面では、多職種を巻き込みながら、患者さんにとって最善の選択肢を模索し続けています。
これは単なる業務ではなく、一人の人間として、家族として患者さんに向き合う姿勢から生まれる行動だと考えています。
家族との絆が教えてくれたもの
長男誕生の試練と喜び
妻との最初の子どもである長男の妊娠・出産は、私たち夫婦にとって多くの試練と学びをもたらしました。
妊娠1ヶ月後からの安静期間、日勤・夜勤をこなしながらの家事全般の担当、そして丸一日仕事をした後に始まった陣痛との長時間の闘い。
陣痛室で意識が飛びそうになりながらも、妻の腰を押し続ける以外にできることがない自分の無力さを感じつつ、それでも全力で支えることの大切さを学びました。
24時間以上経ち、陣痛促進剤使用後、長男がようやく生まれた瞬間、気づけば涙が流れていました。
この経験で初めて、本当の意味での「命の重み」と「家族の絆」を実感しました。
退院後1週間で妻が高熱により入院した3日間は、生まれたばかりの長男を一人で昼夜問わず世話をする貴重な体験となりました。
この時期に培った長男との絆は、今でも私たちの関係の基盤となっています。
そして、何より妻がいなくなってしまうんじゃないかという恐怖を味わったことで、妻がどんなに大切な存在なのかをしっかりと認識することができました。
次男誕生までの道のり
次男の妊娠は、不妊治療を乗り越えた末の待望の妊娠でした。
妊娠がわかっただけで、これ以上ないほどの喜びを感じました。
その後、トータル4ヶ月にわたる安静期間、1週間の入院、引っ越しと重なった時期の体調不良など、長男の時以上の困難がありました。
甘えん坊になった長男のケアと妻の看病を両立する中で、家族を支えることの責任と喜びを深く実感しました。
次男の誕生後に取得した育休期間は、長男の時には見ることができなかった日々の成長をじっくりと見守ることができる貴重な時間となりました。
この経験により、子どもの成長に寄り添うことの重要性と喜びを実感し、それが後の転職決断にもつながりました。
子どもたちのための転職決断
夜勤への長男の反応
次男の育休から復帰後、長男が夜勤で私が家にいないことを次第に嫌がるようになりました。
最初は小さな変化でしたが、徐々にそれが悪化していく様子を見て、父親として何を優先すべきかを真剣に考えました。
友人からの訪問看護への誘いがあったタイミングで、妻に相談したところ「やりたいことなら良いんじゃない」と背中を押してもらいました。
この時、自分が本当にやりたいことは看護という仕事ではなく「子どものためになること」だと気づきました。
新たなステージへ
収入面での不安もありましたが、知識を得ることで解消され、約2ヶ月後に訪問看護ステーションへの転職を実現しました。
現在は、在宅で療養される患者さんとそのご家族に寄り添い、住み慣れた環境で安心して過ごせるようサポートしています。
病院での経験、自身の家族との体験、そして父親としての視点を活かし、患者さんやご家族の気持ちに寄り添った看護を心がけています。
これからの想い
私の看護師としての歩みは、多くの挫折と困難、そして家族との絆に支えられてきました。
これらの経験すべてが、今の私の看護観を形作っています。
最も大切な存在である子どもたちのため、そして私を支えてくれる妻のため、患者さんとそのご家族のため、これからも「ヒトに寄り添う看護者」として成長し続けていきます。
一人ひとりの患者さんを家族のように思い、その人らしい生活を支えることができる看護師でありたいと思っています。
どんな困難があっても、家族との絆と患者さんへの想いを胸に、前進し続けます!